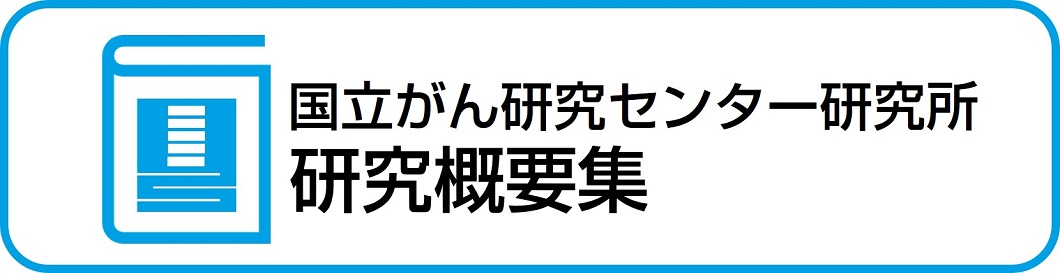トップページ > 研究組織一覧 > 分野・独立ユニットグループ > 希少がん研究分野 > プロテオーム解析のコラム
プロテオーム解析のコラム
プロテオーム解析の現在、過去、未来に関する所感を綴っています。
文責 希少がん研究分野・分野長 近藤格
プロテオーム解析の現状と課題
なぜプロテオーム解析には標準的な技術がないのか
臨床検体を用いたプロテオーム解析は多くの研究者が興味をもつところです。しかし、正確な臨床情報が付随した臨床検体を十分な数だけまとめて使用できる研究グループは世界的にも少ないのが現状です。いきおい、少数の臨床検体を用いた解析があちこちで行われることになります。しかし少数の臨床検体から導き出せる結果には限界があり、間違った結果が導かれがちです。臨床検体を施設間で共有することが一つの解決策ですが、研究に使用できる臨床検体は数だけでなく量も限られているので、実際にはなかなかうまくいきません。もう一つの解決策は、それぞれの施設で採取された実験データを共有するということです。臨床検体を使用する研究に限らず、培養細胞や精製タンパク質を用いた研究であっても、プロテオーム解析のデータをデータベース化して共有できるメリットは大きいと言えます。そのようなときに必須なのが、標準的な技術です。ゲノムやトランスクリプトームの解析では標準的な技術が確立され研究者のコミュニティーで共有されており、データベースが構築されています。公開されているデータベースは世界中の研究者が使っており、共有のメリットは十分に享受されています。しかしプロテオーム解析では標準的な技術は確立されていません。研究者は各自がベストと信じる技術を使用し、データの内容も質もばらばらのまま発表しています。そのようなデータを集めてデータベース化しても、意味のある解析ができるとは思えません。「Garbage In Garbage Out」という格言はここでも当てはまります。標準的な技術が確立されない限り、方々で採取されたプロテオームのデータをデータベース化しても、意味のある解析結果は得られないのではないでしょうか。この問題はプロテオーム解析の黎明期から広く認識されており、解析技術の標準化を目指して過去10年以上にわたり国際的に多大な努力が払われてきました。しかし、プロテオーム解析の標準的な技術は現在に至るまで確立されていません。
プロテオーム解析で標準的な技術が確立されないのはなぜでしょうか?
標準的な技術が確立されない原因はいくつかあります。第一には、タンパク質の多様性にその原因があります。プロテオーム解析では、一つの遺伝子から産生されるタンパク質について、発現量、局在、活性、相互作用、翻訳後修飾など、さまざまな情報を扱うことが求められています。つまり、プロテオームのデータは複雑度がきわめて高いことが特徴です。そして、それぞれの情報についてそれぞれの技術が開発されているので、標準化するべき技術も一つや二つではありません。すなわち、タンパク質の多様性に対応して、標準化するべき技術が多すぎることがまず問題です。
標準的な技術を造ることができない第二の理由は、プロテオーム解析に用いられるサンプルの多様性が高いことです。精製したタンパク質からヒト臨床検体まで、実にさまざまなサンプルがプロテオーム解析の対象になります。精製された純度の高い少数のタンパク質であれば有効な方法であっても、タンパク質以外の雑多な夾雑物が混入した状態のサンプル(血液や腫瘍組織など)だと、その方法の本来の性能を発揮できません。一部の研究者の手ではうまくいく方法でも多くの研究者が使ってみるとうまくいかないのは、研究者ごとに性格が異なるサンプルを使っているところが大きいと考えられます。たとえば、タンパク質のリン酸化状態は手術検体が採取されてから刻一刻と変化していきます。虚血状態がリン酸化に影響すると考えられています。また、腫瘍組織には腫瘍細胞以外の細胞が必ず含まれており、腫瘍組織からどのようにタンパク質を抽出するかによって結果は大きく異なります。また、脂肪や粘液が大量に含まれているヒト組織もありますが、タンパク質の精製は実に難渋します。サンプリングの方法はそれぞれのサンプルに応じて最適化されていくため、そこから標準化する必要があります。しかし、施設ごとに研究環境は異なること、すでに抽出されたタンパク質についてはどうしようもないことなどから、画一的なサンプリング法を押し付けられることは個々の研究者にとっては、余程にメリットがない限り、迷惑千万な話です。まとめると、標準化を推進できる技術系の研究者の想定を超えてサンプルの実際が複雑すぎるということ、そして、あえて標準化すると研究が妨げられてしまうということが、標準化の妨げとなっています。
標準化を妨げる三番目の要因は、プロテオーム解析の技術がいつまでたっても発展段階にあることです。今世紀に入りプロテオーム解析の基本技術である質量分析の精度は著しく向上しました。しかし、プロテオーム解析に向けた装置の最適化は依然として大きな課題として残されています。たとえば、タンパク質のそれぞれの翻訳後修飾を網羅的にどのように解析すると最大公約数的にベストなのか、わかっていません。また、定量的に測定する技術も開発段階であり、タンパク質を切断して得られるペプチドのごく一部を測定できるという原始的な段階です。プロテオームワイドに抗体は作製されたものの、膨大に作製された抗体をどのような方法で一式まとめて使用すれば網羅的解析になるのかについては、未だ模索段階です。分析に用いられる質量分析装置の安定性にも課題が多く残されています。たとえば、全く同じサンプルを複数の研究室に配布し、同一と考えられている技術でプロテオーム解析を行ってみると、果たしてその結果はばらばらだった、という報告が多数あります。このような問題はそれぞれの専門家によって少しずつ解決されていくと考えられます。また、その過程において多くの発見がなされていくことでしょう。しかし、技術が成熟し発展がプラトーに達していなければ、ある時点で標準化された技術はやがて時代遅れになってしまいます。すなわち、プロテオーム解析は、技術的な意味において、まだ標準化を行うべき段階に到達していないのかもしれません。
標準化を妨げる四番目の要素は、プロテオーム解析という分野の多様性です。すなわち、プロテオーム解析はきわめて学際的な分野であり、機器分析の専門家から臨床医までさまざまな方が参加しています。したがって、プロテオーム解析に対していろいろなレベルの要求があります。たとえば、「バイオマーカー解析に応用できる技術」というときの「バイオマーカー」の概念は、分野が異なると全くばらばらです。発現差があるタンパク質をすべてバイオマーカーと考える研究者もいれば、臨床検査として実用化され治療成績の向上に役立つものをバイオマーカーと考える研究者もいます。プロテオーム解析ではタンパク質が同定できさえすればよいと考えている研究者もいれば、同定するとはどういうことなのかを研究している人もいます。標準化を達成するためには、技術要素に優先順位をつけ、ある部分は切り捨てる必要があります。しかし、現在の状況では、標準化において優先するべき技術要素を誰もが納得する基準で決めることがきわめて難しいのです。
過去10数年の国際的な議論において、ここに挙げた問題点は概念としては広く共有されてきたように思われます。結局は、標準化に必要なオールマイティーな技術はまだ造ることができないということでしょう。具体的に的を絞ったプロジェクトを設定し、その中において早期に実現可能な研究テーマに集中すれば、プロテオーム解析技術の標準化は推進されると考えられます。しかし、その場合、標準化の恩恵を受ける研究者の数は多くないかもしれません。プロテオーム解析は対象が大きすぎて茫漠とした議論になりがちです。プロテオーム解析に携わる研究者としては、プロテオーム解析のメリットを最大限に活かすことができる研究テーマとは何か、逆に、プロテオーム解析に求められる研究テーマとは何か、について優先順位をつけてシャープに考えることが求められています。そのような思考の過程において、標準的な技術のあり方がみえてくるのでしょう。
プロテオーム解析の幻想
プロテオーム解析の大きな目標の一つは、できるだけたくさんのタンパク質を観察することです。プロテオミクスという学術用語が創成されたのは1995年、そしてプロテオーム解析が注目され始めたのは今世紀に入りヒトゲノム配列が発表されてからです。「ゲノムの次はプロテオーム」ということで、世界中でプロテオーム研究に膨大な研究費が投下され始めました。2001年にその後のプロテオーム解析の方向を決定するランドマークとなる論文が発表されました(文献1(外部リンク))。その論文では、代表的な血清タンパク質の量を横軸に、その存在量を縦軸にプロットしたシンプルな図が描かれています。この論文はインターネット上にて無料で閲覧できるので、時間があればご覧ください。具体的なメタデータと共に、「プロテオーム解析では量の多いタンパク質しか観察できず既存のバイオマーカーは何もみえない」という主張が明確に打ち出されたことは、特筆に価すると思います。15年経った今でも、「網羅性を向上することがプロテオーム解析の至上命題」という話の中で、この論文は大きな学会ではかならず誰かが引用しています。この論文は、その後のプロテオーム解析の方向性を決めた、ランドマーク的な論文だったと考える所以です。技術開発の方向の一つとして、高い網羅性を追求することはわるい考えではありません。しかし、単に網羅的にデータを集めさえすれば何かがわかるというものではありません。
がん研究におけるプロテオーム解析では、研究課題の本質的な難しさを避けて「網羅性の向上」という技術的な課題に逃げてきた感があります。たとえば、「バイオマーカー解析がうまくいかないのは網羅性が低いからである」という文言は頻繁に論文や学会で見聞きするところです。しかし、バイオマーカー開発では解析の網羅性は成功の必要十分条件ではないことは明らかです。たとえば、ゲノムやトランスクリプトームの解析では高い網羅性をもって解析する技術はとうの昔に完成しています。ことにトランスクリプトームの解析ではDNAマイクロアレイを用いた解析によって数多くのバイオマーカーが報告されてきました。PubMedを「DNAマイクロアレイ」「バイオマーカー」というキーワードで検索してみると、2005年以降、毎年1,000本以上の論文が発表されていることがわかります。一方、過去に10,000本以上の論文があるにも関わらず、DNAマイクロアレイを用いて発見され実用化されたバイオマーカーは少数であり、全体からするとむしろ例外的です(文献2(外部リンク)、文献3(外部リンク))。このことから、ほぼ完璧な網羅性でもって研究をしたとしても、それだけで実用的なバイオマーカーがどんどんできるわけではないことがわかります。ゲノム研究もずいぶん進歩しましたが、臨床的に実用化されるバイオマーカーを見つけることは決して容易ではありません。あと10年くらいすると、今よりも格段の網羅性をもったプロテオーム解析が可能になるのかもしれません。しかし、それだけではバイオマーカーはできないことが、他のオミクス解析の事例からわかります。プロテオーム解析でバイオマーカー開発を行う研究者は、網羅性を高めるだけでは何も解決されない、ということを、今までのほかのオミクス解析の事例から学ぶべきです。
同じようなことは、他の研究課題にもあてはまるかもしれません。重要でありながら誰も解決できていない問題にアプローチするためには、「網羅性の向上」に代表される取り敢えずできる目の前の技術的な課題(そのほかにもたとえば「定量性の向上」「再現性の向上」など)に飛びつくのではなく、問題の本質を深く考えることがポイントなのではないでしょうか。
現代のプロテオーム解析技術が描く歪んだプロテオーム像
プロテオーム解析の技術は多岐にわたり、どれか一つの方法で足りるというオールマイティーな方法は未だ現れていません。使用する技術によってどのようなタンパク質がどのように観察できるのかは、かなり異なっています。したがって、複数の選択肢(技術)の中から研究の目的や環境に応じて使い分けたり組み合わせたりすることになります。過去には「この方法ですべてが解決」と喧伝されたプロテオーム解析の技術はいくつもありました。マスコミや企業はセンセーショナルな表現を好み、技術に明るくないユーザーはついそれに乗ってしまいます。装置を製造販売する企業がプロテオームの学会を強力にサポートしてきたという背景も、ひょっとしたら何かに影響しているのかもしれません。しかし新しい技術を試してみると期待された通りの性能ではないことが多く、新しい技術によって古くからある技術が駆逐された例は過去ほとんどありません。裏を返せば、出たての新しい方法は後の世代には使われなくなるかもしれないという可能性を常に意識しておく必要があります。また、プロテオームのどの側面を観察するかは、どの技術を使用するかによってほぼ決定されます。自分のみているプロテオーム像は、プロテオームのある一面に過ぎないということを常に念頭においた方がよいでしょう。
たとえば、二次元電気泳動法を用いたプロテオーム解析では、電気泳動法の特性にデータが限定されます。すなわち、二次元電気泳動法で観察できるタンパク質とは、(1)ウレアなどで可溶化でき、(2)分子量として10キロダルトンから200キロダルトン、等電点として3から10という特性をもち、(3)発現量が多い順に上位5,000番以内(通常は1,000番以内)のタンパク質、です。二次元電気泳動で観察されるタンパク質はプロテオーム全体を反映した分布状況になっていないことを前提としたデータの解釈が必要でしょう。
質量分析を用いたプロテオーム解析では、タンパク質をあらかじめタンパク質分解酵素(トリプシンなど)で切断してペプチド化してから観察するのが一般的です。翻訳後修飾によって一つの遺伝子から複数のタンパク質が発生するのですが、ことごとくトリプシンで切断してしまうので、翻訳後修飾によってどのようにタンパク質のバリエーションができているかを知ることはできません。質量分析で観察対象となるのは断片化されたペプチドですが、たいていのペプチドはそれぞれの元になるタンパク質のバリエーションの存在量を代表しえません。そして、イオン化される特定のペプチドだけが観察対象になるので、検出されない翻訳後修飾については存在しないから検出されないのか実験系の特性のためなのか、判断できません。質量分析の特性から全長のタンパク質よりもペプチドの方が圧倒的に解析しやすいので、ペプチドの量を測定することで全長タンパク質を測定したかのような発表が学会では当然のように行われています。しかし、このような技術的な特性や限界を意識したデータの解釈が必要です。
抗体を用いたプロテオーム解析では、抗体の性格によって結果が左右されることがあります。たとえば、世界最大の抗体データベースであるHuman Protein Atlas(外部リンク)には、同一の抗原を認識する異なる抗体で免疫染色をした例が数多く収録されています。発現の陽性・陰性や細棒内の局在などは用いる抗体によって相当に異なっていることがわかります。抗体によって明らかに異なる結果が得られたときに、それぞれの裏付けをとる実験を行うなどの工夫が必要です。一つの抗体で何かを結論するのは危険かもしれません。
このように、プロテオーム解析の技術はそれぞれに特性と限界があります。限界やゆらぎをもった「いい加減なデータ」としてプロテオームのデータを扱い、プロテオームの全体像を再構築できるバイオインフォマティクスの技術が望まれます。それにしても、自分たちのみているプロテオーム像は、技術的なバイアスが相当にかかっていることを常に認識するべきです。

出典:1942 June 3, Florence Morning News, Mutt and Jeff Comic Strip, Page 7, Florence, South Carolina.
この図は「under the street light joke」として有名な風刺画です(「quarter:25セント」が「鍵」になっているバリエーションもあります)。街頭の下で一生懸命にコインを探している男性は、コインが街灯の下にあると思ってそうしているのではなく、街灯の下が明るくて探しやすいという理由でそうしている、という笑い話です。プロテオーム解析も似たようなことになっているような気がします。研究者は、市販の技術が見せてくれるプロテオームを見るだけではなく、見る価値のあるプロテオームを自分で決めて見にいく存在でありたいものです。
「網羅的な解析」「仮説に基づかない解析」は本当によいのか?
プロテオーム解析に関連する論文や学会では、網羅的であること、仮説に基づかない解析であること、があたかも優れたアプローチであるかのように語られています。「先入観にとらわれずに網羅的に解析した結果なのだから、そこからは客観的な結果を導き出せる」という考えです。しかし、上述のように、解析技術として何を選択するかによって観察されるプロテオーム像は相当に変わってきますので、この考え方はかなり疑わしいと言わざるを得ません。この考え方がおかしい理由は他にもあります。
まず、「網羅的な解析」はプロテオーム解析では実施できていません。プロテオーム解析でいう「網羅的」とは、「できるだけたくさんのタンパク質を解析した」という意味でしかありません。「できるだけ」といっても現代の最高技術レベルで解析したわけではなく、その研究者の最大努力を意味しているだけなので、学術的には何の意味もない言葉です。
その研究テーマについて過去の研究の蓄積が何もない場合には、「仮説に基づかない」アプローチを取らざるを得ないかもしれません。しかし、がん研究のように膨大な知見の蓄積がある場合、積極的に過去の研究成果を利用するべきではないでしょうか。プロテオーム解析では特定の技術で全体を網羅することができないので、どの技術を用いるかが研究の成否を分ける因子になるかもしれません。したがって、仮説に基づいて技術を選択しないと、がんのプロテオーム解析は疑似科学になりかねません。がん研究に詳しくない研究者にとっては、仮設に基づかないアプローチをとらざるを得ないのではありますが、仮説に基づかず手ぶら状態で解析するのは、研究課題によってはかなり無謀、時間とお金の無駄になりかねません。
プロテオーム解析の業界は長年にわたって「言わなくてもわかるだろう」というハイコンテクストな文化が形成されてしまっています。プロテオーム解析では、論文や学会での常識の一つ一つを疑ってみる姿勢が必要です。
プロテオーム解析によるバイオマーカー開発の問題点
成功するバイオマーカー開発
バイオマーカー開発はプロテオーム解析の分野ではメジャーな研究テーマであり、バイオマーカー開発をタイトルに冠した大きな国際学会がいくつも開催され、論文も毎年1,000本以上が発表されています。一方、プロテオーム解析で開発されて実用化されたバイオマーカーはきわめて希です。たとえば、プロテオーム解析で開発されFDAで承認されたバイオマーカーは数えるほどしかありません(後述)。プロテオーム解析で発見され臨床試験の途上にあるバイオマーカーは数多くあると思われますが、それにしても商業化されたバイオマーカーは希ですし、治療成績の向上に実際に寄与したバイオマーカーは皆無です。プロテオーム解析によるバイオマーカー開発の問題点は多くの総説や講演で取り上げられてきました。曰く、サンプル数が少ない、検証実験が行われない、使用用途が明確でない、測定が安価にできない、など。指摘されていることはすべて正しく、すべてを解決しない限りバイオマーカー開発は成功しないのでしょう。たくさんある課題がある場合はまず優先順位をつけ、優先度の順に最適なアプローチを探す必要があります。
プロテオーム解析で発見されFDAで承認されたバイオマーカーとして、「Ova1」と命名された卵巣がんの診断マーカーがあります。Ova 1は卵巣がんの診断バイオマーカーですが、早期診断のスクリーニングをするためのバイオマーカーではありません。骨盤内に腫瘍があったときに、良性か悪性かを鑑別するためのバイオマーカーです(文献4(外部リンク))。Ova1の開発者は婦人科腫瘍を専門とする臨床医との長時間にわたる話し合いでこの研究課題を知ることになりました(文献5(外部リンク))。解析は、John’s Hopkins大学のDaniel Chen教授らによって行われましたが、画像検査を受けた方を対象とした卵巣がんのこのような研究課題は、ふつうに基礎研究をする研究者が知ることはまずないでしょう。臨床医と研究者が話し合うことでみつかる、プロテオーム解析で解決可能な臨床的な問題は少なくないと思われます。どのようなバイオマーカーが求められているのか、というマーケティングがまず何よりも必要でしょう。そして、そのために必要な技術は何か、すなわちどのようなイノベーションが必要なのかを考えるにあたり、相談できる臨床医や病理医のパートナーをみつけることが、研究の最初の段階からまず必要ではないでしょうか。
早期診断のバイオマーカー開発の問題点
プロテオーム解析による早期診断のバイオマーカー開発は盛んに行われています。使われるのは血液のサンプルです。腫瘍組織よりも血液サンプルの方が一般に入手し易いため、早期診断のバイオマーカー開発は始めやすいのかもしれません。検診のためのバイオマーカーということで、がん患者と健常者のサンプルを比較し、高い感度・特異度を示す早期診断のバイオマーカーがプロテオーム解析で発表されてきました。(肺がんの例、文献6(外部リンク))。プロテオーム解析で発見された感度・特異度が素晴らしいバイオマーカーが多数発見されていますが、早期診断を目的とした検診で使われるようになった例はありません。
プロテオーム解析による比較実験でバイオマーカーの候補を見つけようとする場合、多くはほぼ同数のがん患者と健常者のサンプルが比較されます。そして、その結果を元にバイオマーカーが同定され、感度・特異度が計算されます。何も疾患をもたない健常者の方のサンプルががん患者さんのサンプルのコントロールになりうるのか、という医学的な問題もさることながら、検診を受ける集団にほぼ同数のがん患者と健常者が含まれることはありません。検診を受ける集団では、がんを患っていない方がほぼ全員です。全国的にも、年齢で層別化しなければ、ある特定のタイプのがんの患者さんというのは全体的には1000人に1人以下の頻度でしかおられません。したがって、同数のがん患者と健常者との比較で算出された感度や特異度をそのまま現実世界に当てはめると、膨大に偽陽性が発生してしまいます。すなわち、あるバイオマーカーでがんと診断された方のほとんどはその後の検査でがんでないことになりうる、ということです(文献7 (外部リンク))。
これはプロテオーム解析に限ったことではなく、検診における早期診断のためのバイオマーカー開発の一般的な問題です。プロテオーム解析を工夫して解決できる問題ではありません。ハイリスクグループをあらかじめ特定できるようなテーマでないと、早期診断のバイオマーカー開発は難しいのではないでしょうか。プロテオーム解析を行う研究者の間でこの問題が意識されることはほとんどなく、実験室でしか通用しないバイオマーカーが論文化されているが現状です。バイオマーカー開発はペプチドやタンパク質や翻訳後修飾の研究ではなく、疾患研究であることを意識する必要があると言えます。
プロテオーム解析に関連する学会の紹介
プロテオーム解析に関連する学会としてもっとも規模が大きいのは、Human Proteome Organization(HUPO)です。2002年に第1回がベルサイユ(フランス)で開催され、それ以来、毎年一回のペースで、米国、ヨーロッパ、アジア・オセアニアと持ち回りで学術大会が開催されています。日本でも2013年に第12回が横浜で開催されました。2018年は第17回がオーランド(米国)で開催されました。2019年に第18回がアデレード(オーストラリア)で開催されます。HUPOのように複数の国が持ち回りで主催する国際学会としては、西ヨーロッパの研究者が主催するEuropean Proteome Association(EuPA)、中央・東ヨーロッパの研究者が組織するCentral and Eastern European Proteomics Conference(CEEPC)、そしてアジア・オセアニア地域のAsia Oceania Human Proteome Organization(AOHUPO)あります。
2018年度のAOHUPOの年会は大阪で開催されました。国別では、ヨーロッパ地域では、ドイツの研究者が組織するGerman Society for Proteome Research (Deutsche Gesellschaft fur Proteomforschung e.V. (DGPF))があり、Proteomics Forumが開催されています。また、イギリスのBritish Society for Proteome Research (BSPR)、スウェーデンのSwedish Human Proteome Organization (SPS)、スイスのSwiss Proteomics Society (SPS)も、学術大会を長年にわたり開催しています。北米では、アメリカの研究者が組織するUS Human Proteome Organization (US HUPO)とカナダのCanadian National Proteomics Network (CNPN)が知られています。
アジア・オセアニア地域では、後述する日本の学会に加え、中国のChinese Human Proteome Organization (CNHUPO)(、台湾のTaiwan Proteomics Society (TPS)、韓国のKorea Human Proteome Organization (KHUPO)、そして、オーストラリア・ニュージーランドのAustralasian Proteomics Societyなどが活動的です。
そのほか、小規模なプロテオーム解析の学会が、欧米やアジアの各国で開催されています。大きな会が必ずしもよいわけではなく、規模は小さくても記憶に残る素晴らしい会は多数あります。例えば、イタリアのシエナで隔年に開催されていたSiena Meetingは、発表のレベルが高く、トスカーナ地方の風光明媚な風景と美味しい料理・ワインと相まって、忘れられない会の一つです。印象的な懇親会もたくさんあって、有名な美術館や博物館、そして歴史的な建造物を貸し切りにして行われる懇親会も、海外では珍しくありません。中世の建物の中やピカソの絵を目の前にして味わうワインは格別です。私は海外の学会によく参加するのですが、それぞれの地域の文化や研究者の気質(国民性)がプログラムや懇親会に反映されている印象を受けます。外国を訪れ海外の研究者と交流することで、他では得られないよい刺激を得ることができます。多様な考え方に触れ新しい発想を得るために、大学院生や若い研究者はいろいろな国際学会にどんどん参加していただきたいものです。

プロテオミクスに関連する本邦の学会・研究会としては、日本プロテオーム学会が組織されており、毎年、学術大会が毎年開催されています。ゲノム研究とプロテオーム研究の融合(proteogenomics)が最近のトピックスで、上述のHUPOを活動の場として米国がんセンターはInternational Cancer Proteogenoics Consortium (ICPC)を組織しました。
このような世界的な流れを受け、2005 年に発足した日本臨床プロテオーム研究会は、2017年に日本臨床プロテオゲノミクス研究会と改名しました。日本臨床プロテオゲノミクス研究会は基礎の研究会にも関わらず会員の多くが臨床医であるという特色があります。臨床に役立つ研究を目指す研究者はどのように研究を行っているのかということについて、興味のある方はぜひご参加ください。