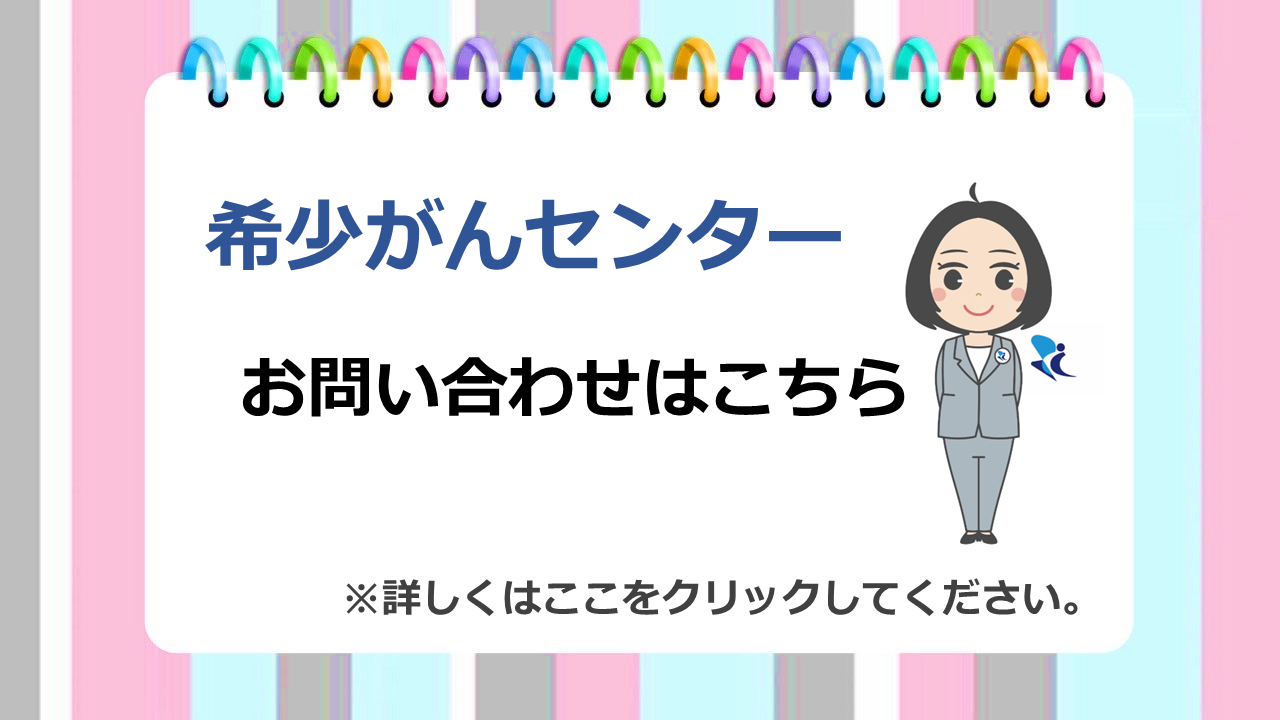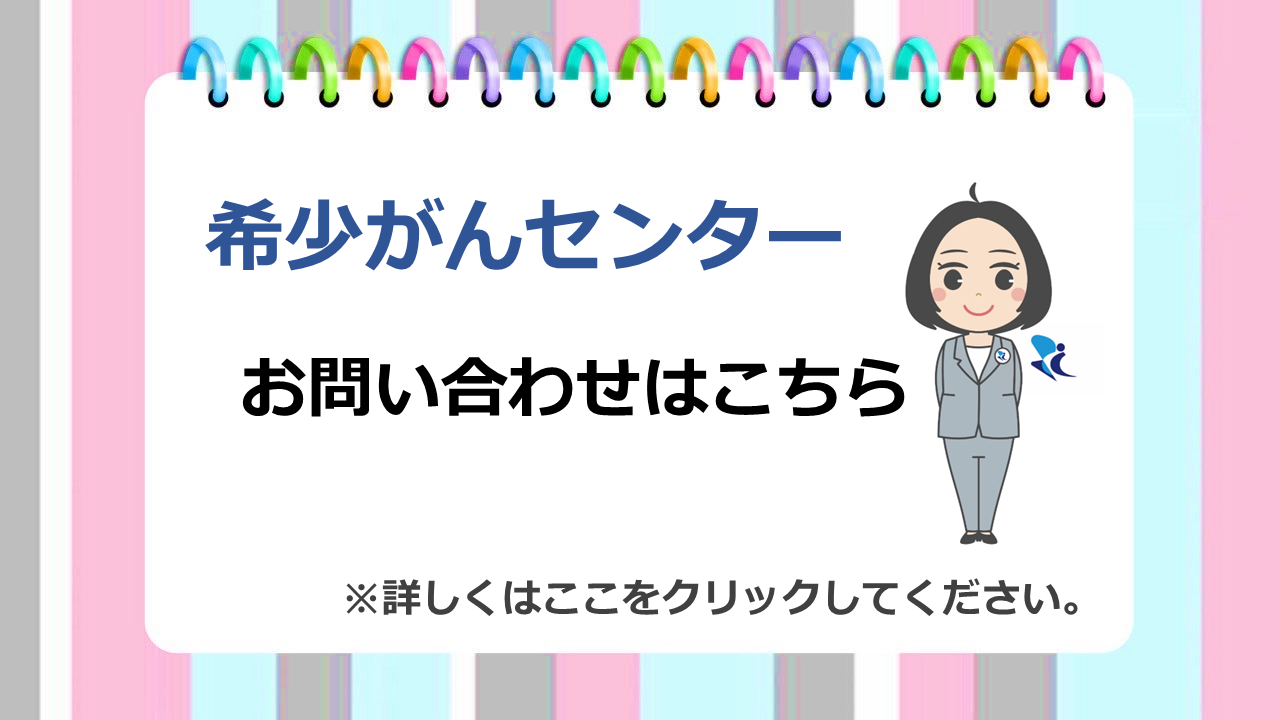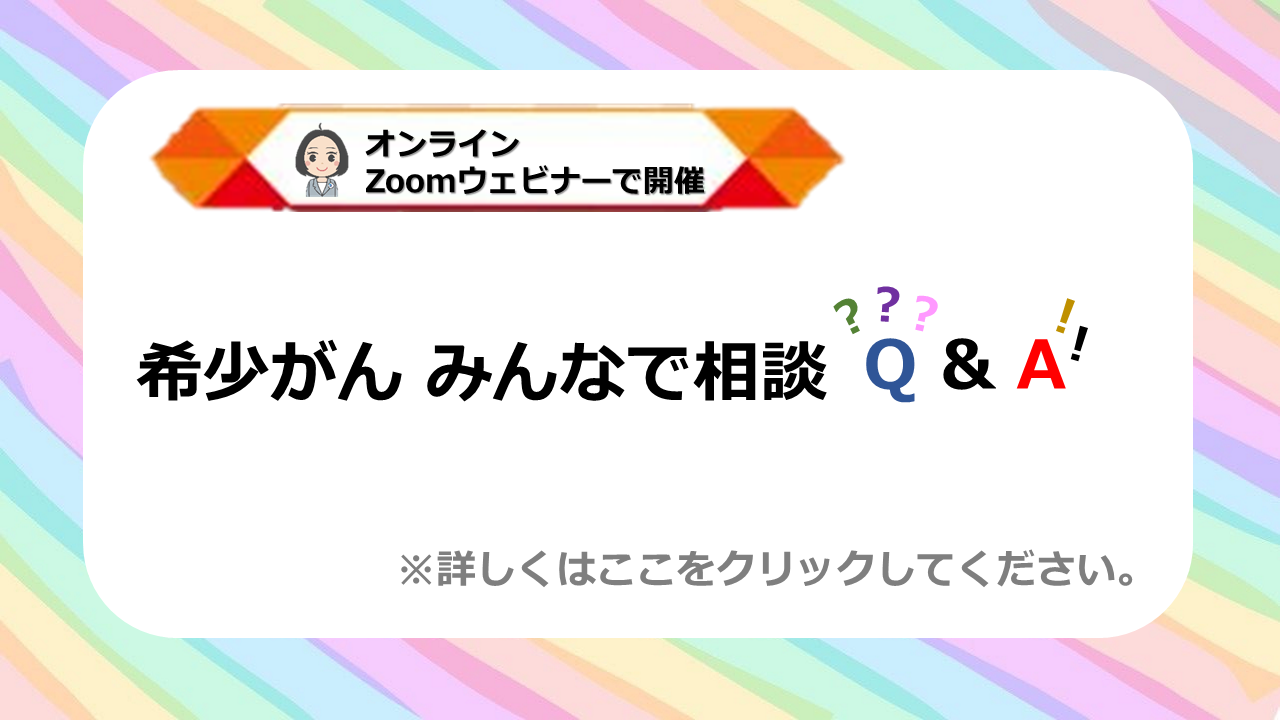トップページ > さまざまな希少がんの解説 > 骨肉腫(こつにくしゅ)
骨肉腫(こつにくしゅ)
更新日 : 2024年5月28日
公開日:2024年5月28日
概念・定義
骨肉腫(osteosarcoma)は、病理組織学的に腫瘍性の類骨・骨を形成する悪性腫瘍と定義されます。通常型骨肉腫が最も一般的ですが、頻度の低い亜型として血管拡張型骨肉腫、小細胞型骨肉腫、低悪性度中心性骨肉腫、放射線照射後やPaget病に続発する二次性骨肉腫もあります。
疫学
本邦における骨肉腫の発生頻度は人口100万人あたり1~1.5人程度です。日本整形外科学会・国立がん研究センターによる全国骨腫瘍登録の統計では、日本全国で新規に登録された骨肉腫の患者は177名(2021年)、168名(2022年)であり、これは原発性悪性骨腫瘍全体の約25%を占め、原発性悪性骨腫瘍の中で最も発生頻度が高い腫瘍です。
骨肉腫の罹患は10~20歳代で多く(約60%)、若年者に好発しますが、40歳以上も約30%を占めます。40歳以上での発症例の中には小児期における放射線治療やPaget病による二次性骨肉腫と考えられるものもあります。男女比は1.5 : 1とやや男性に好発します。
好発部位は長管骨の骨幹端(骨の端から少し骨幹によった所)であり、大腿骨遠位、脛骨近位、上腕骨近位の順に好発します。脊椎や骨盤に発生することもありますが、その多くは中高年者に発症することが知られています。
診断
他の原発性悪性骨腫瘍と同様、生検(腫瘍の一部を採取すること)を行い、病理組織学的に診断します。腫瘍性の類骨・骨を顕微鏡で確認することにより骨肉腫と診断されます。
病因
病因は不明であり、原因となる特定の遺伝子異常は明らかになっていません。近年、がん抑制遺伝子であるRb遺伝子やp53遺伝子を含む染色体に異常が認められることが明らかになっており、これらの遺伝子の働きが消失することが骨肉腫の発症に関わると考えられています。また、網膜芽細胞腫の二次癌の多くが骨肉腫であることや、家族性にがんを多発する遺伝症候群であるLi-Fraumeni症候群で骨肉腫を高率に発症することが知られています。
症状
数週間から数ヶ月持続する局所の疼痛や腫脹で発症します。疼痛は、はじめは運動時痛や歩行時の痛みですが、次第に安静時にも痛みを感じるようになります。好発部位が大腿骨遠位、脛骨近位、上腕骨近位であることから、膝や肩周囲の疼痛や腫脹を主訴に受診に至る例がしばしばみられます。転倒やつまずきなどの軽微な外力による骨折(病的骨折)を生じて見つかることもあります。診断時に10~20%の症例で肺などへの遠隔転移を認めますが、病変としては小さいものが多く、多くの場合、転移巣に関する症状はありません。
血液検査ではしばしばアルカリフォスファターゼ(ALP)の上昇を認め、このような症例ではALPは術前化学療法に対する反応や治療終了後の経過観察における再発や転移の指標として用いられます。
治療
治療は切除可能例と完全切除不能例(多発転移例など)にわけて考えます。
現在の骨肉腫に対する標準治療は、切除可能例では、手術による局所の根治と術前・術後化学療法による肺転移(微小転移)の制御を組み合わせた集学的治療です。治療期間は約9か月程度になります。
化学療法
1970年代以前は、骨肉腫に対する治療は患肢切断による手術療法のみが行われていました。しかし、手術により完全に局所制御が得られたにも関わらず、多くの場合、術後1年以内に肺転移を生じ、5年生存率は5~10%と極めて不良でした。1970年代以降、再発・進行骨肉腫に対する化学療法の有効性が次々と報告され、初回治療の骨肉腫に対しても手術と化学療法を組み合わせた治療が行われるようになりました。
骨肉腫に対するキードラッグはメトトレキサート大量療法(HD-MTX)、ドキソルビシン(DOX)、シスプラチン(CDDP)です(MAP療法)。
標準治療であるMAP療法からさらなる治療成績向上を目指して、欧米の国際共同研究 The European and American Osteosarcoma Study Group I Trial(EURAMOS I)や本邦における JCOG0905などの臨床試験が行われましたが、いずれもMAP療法を上回る治療成績を得ることはできませんでした。
完全切除不能例(多発転移例など)では、イホスファミド(IFO)、IFOとEtoposide(VP-16)の併用(IE療法)、IFO、Etoposide(VP-16)とcarboplatinの併用(ICE療法)、GemcitabineとDocetaxelの併用(GD療法)などによる治療が行われ、奏効割合は15.6%から62.5%と報告されています。
手術
骨肉腫に対する手術は、広範切除術(腫瘍細胞を取り残さないために、腫瘍を正常な組織で包み込んで一塊として切除すること)が基本です。適切な広範切除術が行われた場合には、切断術とほぼ同等の局所根治性を得ることができます。
現在、四肢に生じた骨肉腫に対する患肢温存率は90%程度に達していますが、腫瘍が重要な神経や血管を巻き込んでいる場合などでは、切断を選択せざるを得ないこともあります。
以下に患肢温存手術の具体例を示します。
大腿骨遠位骨肉腫の人工関節による患肢温存術
凍結処理骨を用いて関節温存を行った手術
自分自身の腓骨を移植することで関節を温存した手術
予後
骨肉腫では、治療後も定期的に通院し、再発や転移が生じていないか診察を受けることが大切です。小児の場合は成長に伴って生じる手足の長さの左右差(脚長差)に対する治療を検討する必要もあります。
化学療法の導入により、初診時に遠隔転移のない症例の5年全生存率は70~80%程度と大きく改善しました。しかし、初診時に遠隔転移のある症例や治療後に再発・転移を来した場合には依然予後不良です。
転移病変が完全に切除された場合の長期生存は40%程度と報告されており、転移病変の切除可能例に対しては、積極的な外科的治療を考慮すべきであると考えられています。
予後の改善に伴い、サバイバーにおいては化学療法に関連した晩期の有害事象を念頭においた長期間のフォローアップも重要になっています。具体的には、心筋障害、腎障害、聴覚障害、不妊、白血病などの二次がんなどが晩期の有害事象として知られています。その頻度や予防法などに関する検討は今後の重要な課題と考えられます.
骨肉腫に対する化学療法では、晩期障害として性腺機能を低下させるCDDPやIFOを用いるため、化学療法を行う小児期、AYA世代の患者では、妊孕性温存(精子保存など)を検討することも重要です。
治療開発における最新の動向
大規模なゲノム研究により、骨肉腫では約40%の症例で染色体の4q12や6p12などの特定部位に遺伝子増幅が存在し、それらの遺伝子を標的とした分子標的治療が有効である可能性が示唆されました。これらの知見を背景に、近年、sorafenib、cabozantinib、regorafenibなどのマルチチロシンキナーゼ阻害薬(mTKI)の臨床開発が進められています。
本邦ではmTKIであるpamufetinib(TAS-115)の治療開発が進められ、「進行・再発骨肉腫患者を対象としたTAS-115の第III相試験」が国立がん研究センター中央病院などにおいて実施されています。
しかし、骨肉腫の治療開発においては、その希少性のために、検証的なランダム化比較試験を実施することが困難であることや、コントロール(外部対照)となるデータが存在しないことが大きな障壁となっています。
薬事承認に要求される精度でレジストリを構築し、外部対照として利用できるようになれば、治療開発時の貴重な資料となることから、現在、日本臨床腫瘍研究グループ(Japan Clinical Oncology Group:JCOG)骨軟部腫瘍グループと、希少がんの研究開発およびゲノム医療を推進する産学共同プロジェクトである MASTER KEY プロジェクトが共同でMASTER KEY Boneという新しいレジストリ研究を計画中です。
希少がんリーフレット
準備中
相談先・病院を探す
情報や病院などが見つからないときにはご相談ください。
執筆協力者

- 小倉 浩一(おぐら こういち)
- 国立がん研究センター中央病院
- 骨軟部腫瘍・リハビリテーション科