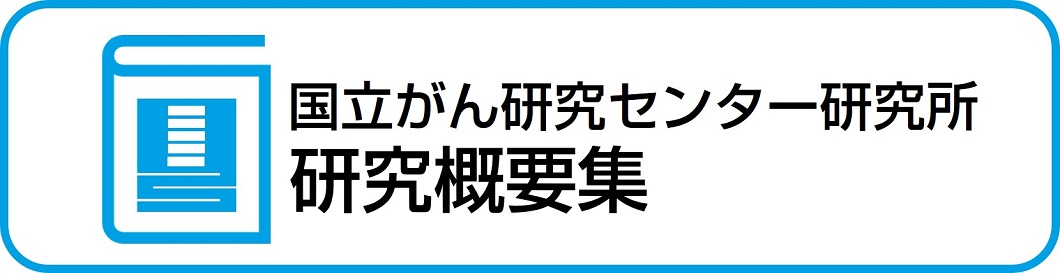トップページ > 研究組織一覧 > 分野・独立ユニットグループ > 生物情報学分野 > 2025年7月以前
2025年7月以前
研究室の紹介
本研究室の名前は”生物情報学”分野、生物情報学はカタカナ英語で言えば、“バイオインフォマティクス”です。”バイオ”と”インフォマティクス”、すなわち生物学と情報学が融合した、新興の学問分野です。専らコンピュータによる実験データ分析を通して、生物の研究をする学問分野です。
研究室主宰者は1970 年代の生まれですが、一説ではバイオインフォマティクスは1970 年代に誕生したと言われています。当時タンパク質のアミノ酸配列が少しずつ明らかにされるようになり、それまでの生物物理学的見方・分子進化学的見方から一足跳躍し、アミノ酸配列を記号と見なす見方が成立してきました。実際に実験をせずとも、あるいは方程式を解かずとも、記号に対する演算を施すだけで、生物学的な情報を得られるという技術(ホモロジー検索)が成立してきたのです。そのことが、それら2系統の学問を始祖としてバイオインフォマティクスが誕生した出来事だったと、研究室主宰者は考えています。一旦ものの見方が変わるとその情報的側面が先鋭化し、その後は情報科学、さらにその後は統計科学の影響も大きく受けながらバイオインフォマティクスは発展して行ったと考えています(コラム 1)。
研究室主宰者が研究キャリアを始めるころからすでに、生物学研究においては新しいハイスループット実験技術が次々と登場して大量のデータが生み出されてきました。がん研究も基本的にこの流れの影響を受けます。とくに2008 年頃から本格的に使用されるようになった次世代シークエンサーの登場は大きいでしょう。染色体上の位置をあらかじめ決めずにDNA 配列を決定できるので、どの位置にも起こりうる体細胞変異のがん研究と親和性が高いのです。大量データが得られたらそれを処理して生物学的に意味のある情報を抽出する必要がありますから、そこではバイオインフォマティクスによるデータ分析が本質的な役割を演じることになります。特にがんゲノム学という研究分野で、さらにはがんゲノム医療のような実用的な分野においても、本質的役割が求められています。いまやこの学問をどう活かすかによって、研究や開発の成否が決まるほど大事な分野となってきました(とはいえ少なくとも本邦では、依然バイオインフォマティクス専門家は不足しています…コラム 2)。
当研究室では、がんを中心対象に、生物情報学を基礎から応用まで展開しています。詳しくは研究プロジェクトで解説しますが、研究の成果を国民皆保険下での本格的な臨床実用まで持って行った、日本で最初のゲノム生物情報学の研究室と考えています。もちろんこれは当研究室単独で達成できたことではなく、共同研究の中で相乗効果によって達成できたことであります。研究をしていると通例、臨床実用の視点を失いがちになりますが、当研究室は臨床実用の視点を常に心に留めながら研究していく、珍しい生物情報学の研究室です(コラム 3)。
本研究室のミッションは以下です。
- がん研究・医療のための新しいバイオインフォマティクス技術の開発およびデータ分析
- データ分析と計算機的手法による新しい数理生物学理論の構築
- 他研究室・他機関への共同研究を介したバイオインフォマティクス・データ分析
臨床応用を常に心に留めながら、批判を恐れず独自の研究テーマを育て、一方、本流に乗る共同研究を進めています。最新の実験技術や解析技術を積極的に取り入れながら(コラム 4)、世界的な視点の中で新しいがんのバイオインフォマティクスを創り出していきたいと考えています。具体的には、研究プロジェクトにあるような研究プロジェクトを実施しています。