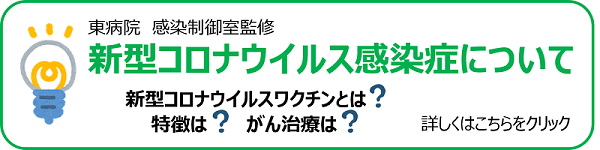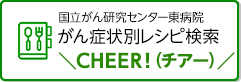トップページ > 共通部門のご案内 > 医療安全管理部門 > 感染制御室 > 新型コロナウイルス感染症について > 新型コロナウイルス感染症の基礎知識
新型コロナウイルス感染症の基礎知識
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の一般的な特徴
- 咳などの呼吸器症状が中心で、多くは軽症だが一部重症化することもある。
- 初期は一般的な風邪症候群やインフルエンザとの区別が困難な症状(発熱や咳など)だが、改善無く持続悪化する場合は注意が必要。
- 発熱や咳などがない患者さんも多いため、発熱や咳がなくても体調がすぐれない場合には新型コロナウイルス感染症への注意が必要。
- 感染後も数カ月にわたって症状が持続したり、感染からしばらくして新たな症状が出現したり再発する場合もある(罹患後症状)。
感染初期から感染中の主な症状
発熱や咽頭痛、鼻汁、咳など

新型コロナウイルスに感染し、発症した際の症状は発熱や咽頭痛、鼻汁、咳など、通常の風邪と見分けがつきにくいことが多いとされています。ウイルスに感染しても少なくとも3の1は無症状との報告があります。[1]
オミクロン株以降のデータでも56%が感染したことに気がついていなかったという報告もあります。[2]
<参考文献>
[1]MaQらの報告(JAMA Netw Open.2021) (外部サイトにリンクします)
[2]Joung SYらの報告(JAMA Netw Open.2022) (外部サイトにリンクします)
罹患後症状(後遺症)
罹患後症状とは
新型コロナウイルスに感染後も、他に明らかな原因のない症状が持続したり、新たに出現、再発することを指します。
がん患者さんにおける罹患後症状の合併頻度はオミクロン株の流行になって低下した(デルタ株までは約19‐17%→オミクロン株では6.2%)との報告がありますが、罹患後症状がある場合にはがん薬物療法を計画通り進めることが難しくなる場合もあります。[3]
新型コロナウイルス感染症に2回、3回と感染をすると...
新型コロナウイルス感染症に2回、3回と感染をすると、重症化のリスクとともに、罹患後症状のリスクも高まることが示されていますので[4]、感染から回復した後も、引き続き感染予防が重要となります。
<参考文献>
[3]Cortellini Aらの報告(Lancet Oncol. 2023)(外部サイトにリンクします)
[4]Bowe Bらの報告(Nat Med. 2022)(外部サイトにリンクします)
コロナ感染症の重症化や死亡について
2022年以降、オミクロン株が流行の主体になってからは重症化や死亡の割合は以前と比べて低下しており、重症化は50歳代以下では0.03%、60~70歳代では0.26%、80歳代以上で1.86%となっており、死亡は50歳代以下では0.01%以下、60~70歳代で0.18%、80歳代以上で1.69%と報告されています。[5]
ただし、感染者数が多い場合には、重症化率が低下しても患者数増加に伴い重症者数の絶対数が増加する可能性もあり、また変異株によっても様々な要素が変化する可能性があるため引き続き注意が必要です。
<参考文献>
[5]令和4年12月21日新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード 資料4 (リンク先でPDFが開きます)
重症例となるリスク
高齢であったり他の疾患がある方は注意が必要
重症化に影響を与える因子

- 年齢(高齢であること)
- 基礎疾患の有無
- 慢性腎臓病
- 心疾患(虚血性心疾患や心不全や心筋症など)
- 呼吸器疾患(間質性肺疾患、気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患など)
- 肥満
- 妊娠
- 喫煙(過去の喫煙歴も含む)
重症化に関しては年齢(高齢であること)が最も強い影響を与える因子として知られますが、それ以外にも基礎疾患の有無が重要です。がんは重症化する因子の1つとして挙げられています[6.7]。がん患者さんは、特にがん薬物療法中など重症化のリスクが高い時期は新型コロナウイルス感染症にかからないようにより注意する必要があります。
その他にも慢性腎臓病や心疾患(虚血性心疾患や心不全や心筋症など)、呼吸器疾患(間質性肺疾患、気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患など)、肥満、妊娠、喫煙(過去の喫煙歴も含む)なども重症化と関連することが知られています[4]。
<参考文献>
[4]Bowe Bらの報告(Nat Med. 2022)(外部サイトにリンクします)
[6.7]Turtle Lらの報告(Lancet Oncol. 2024)(外部サイトにリンクします)