トップページ > 診療科 > 緩和医療科 > 研修プログラムについて
研修プログラムについて
更新日 : 2025年5月20日
最高峰の施設で最先端の緩和ケアを学びませんか?
人材育成のポイント 緩和ケアチーム診療実績 研修の特色 研修のメリット 研修実績
当科レジデントの論文・学会業績 レジデントプログラム紹介 問い合わせ先 PDF資料
人材育成のポイント
緩和ケアは、あらゆる分野において基本的医療として求められ、がん診療においては、診断時から、がん治療期、緩和・療養期とあらゆる時期に必要とされます。また、がん以外の疾患 においても必要とされる医療で、広く普及してきました。しかしながら、緩和ケアの専門家はまだ少なく、基礎・臨床研究も発展途上です。
国立がん研究センター中央病院緩和医療科では、がん診療を中心としたハイスキルの緩和ケアの専門家を育成することを目指し、日々の臨床、研究、教育にスタッフ一同取り組んでいます。当院では早期からの緩和ケアを実践する豊富なチーム介入実績とチーム医療を担う各領域の専門家とのコラボレーション研修を経験でき、当院独自の緩和ケア臨床経験と指導医の丁寧な指導を受けることができます。また、当院にはない緩和ケア病棟や在宅医療、非がん緩和ケアを院外研修として研修できる体制としております。緩和ケア専門医、認定医を目指す方はもちろん、これから緩和ケアを専門にしていきたい方、緩和ケアのスキルアップを求める方も歓迎いたします。
緩和ケアチーム診療実績
2024年度介入依頼内容
合計 2,577 件(内訳:成人 2,518 件、小児 59 件)
| 疼痛 | 1276件 |
| 疼痛以外の身体症状 | 636件 |
| 精神症状 | 1402件 |
| 家族ケア | 98件 |
| 倫理的問題 | 2件 |
| 地域連携・退院支援 | 42件 |
| その他 | 42件 |
介入時期
| 診断から初期治療前 | 512件 |
| がん治療中 | 1691件 |
| がん治療終了後 | 311件 |
| 根治後 | 16件 |
研修の特色
非常に多い症例数
非常に多くの症例数を通じて、短期間でも多くの経験を積むことができます。
ここにしかない多職種チーム
子ども支援、鍼灸治療、アピアランスケアなど他施設ではあまり行われないケアも行っています。
緩和ケア病棟の研修も可能
当院に緩和ケア病棟はありませんが、近隣の施設(国立がん研究センター東病院、がん研有明病院、聖路加国際病院、東京逓信病院など)での緩和ケア病棟研修が可能です。
多数の臨床研究
国際共同研究、国内多施設研究を多数行っています。学会発表や論文執筆はもちろんのこと、緩和支持療法の研究の企画、運営、実施に携わることも可能です。
研修のメリット
当科の研修で下記の資格の要件を達成可能です。
緩和医療学会専門医
- 認定研修施設で2年以上の緩和医療の臨床研修
- 20 例の症例報告
- 緩和医療に関する教育歴(2件以上)
- 緩和医療に関する筆頭の論文と学会発表
緩和医療学会認定医
- 専門的緩和ケアの現場で6か月以上の臨床経験
- 50 例以上の症例を担当
- 5例の症例報告
研修実績
2010年から2024年
がん専門修練医5名
レジデント5名
短期研修医11名
任意研修(他院所属のまま研修)29 名
研修後の進路
国立がん研究センター中央病院 緩和医療科
国立がん研究センター東病院 緩和医療科
青森県立中央病院 緩和ケア科
医療法人社団栄悠会 綾瀬循環器病院
永寿総合病院 緩和ケア科
大阪医科薬科大学病院 緩和ケアセンター
聖路加国際病院
都立駒込病院 緩和医療科
長岡赤十字病院 緩和ケア科
ふくろうクリニック等々力
横浜市立大学附属病院 緩和医療科
横浜南共済病院 緩和支持療法科
わたクリニック
当科レジデントの論文・学会業績
2024年度
- Takeda Y, Ishiki H, Oyamada S, Otani H, Maeda I, Yamaguchi T, Hamano J, Mori M, Morita T. Symptoms and Prognoses of Patients With Breast Cancer and Malignant Wounds in Palliative Care Units: The Multicenter, Prospective, Observational EASED Study. Am J Hosp Palliat Care. 2024 Dec;41(12):1373-1379.
- Takamizawa S, Ishiki H, Takeda Y, Arakawa S, Kawasaki N, Maeda I, Yokomichi N, Yamaguchi T, Otani H, Morita T, Satomi E, Mori M. Prognostic Impact of Malignant Wounds in Patients With Head and Neck Cancer: Secondary Analysis of a Prospective Cohort Study. Cancer Control. 2024 Jan-Dec:31:10732748241274216.
- Ikegami T, Ishiki H, Kadono T, Ito T, Yokomichi N. Narrative review of malignant ascites: epidemiology,pathophysiology, assessment, and treatment. Ann Palliat Med. 2024 Jul;13(4):842-857.
- Toda Y, Ishiki H, Kawasaki N, Arakawa S, Satomi E. Opioids for back and neck pain: the OPAL trial. Lancet. 2024 Jun 1;403(10442):2378-2379.
- Takamizawa, S., Ishiki, H., Oyamada, S., Takeda, Y., Kiuchi, D., Amano, K., Matsuda, Y., Yokomichi, N., Kohara, H., Suzuki, K., Satomi, E. & Mori, M. Psychological symptom burden associated with malignant wounds: Secondary analysis of a prospective cohort study. Palliat Support Care. 2024 Apr;22(2):396-403.
- 池上貴子, 松原奈穂, 石川彩夏, 川崎成章, 荒川さやか, 石木寛人, 伊東山舞, 横山和樹, 里見絵理子. 左鼻腔がん頭蓋内浸潤に起因する難治性がん性神経障害性疼痛に対し、五苓散が症状緩和に有効だった一例. Palliat Care Res 2024; 19(3): 175–180
- 石川彩夏, 石木寛人, 松原奈穂, 池上貴子, 川崎成章, 荒川さやか, 池長奈美, 飯田郁実, 近藤麗子, 里見絵理子. がん疼痛治療におけるオピオイド過量症状に対してナロキソンを用いた症例の検討. Palliative Care Res 2024; 19(4): 237-243
- 阿部晃子, 浜野淳, 里見絵理子, 住谷智恵子, 竹田雄馬, 川越正平. 在宅がん患者の終末期過活動せん妄に対する薬物治療の実態調査. 日本在宅医療連合学会誌(2435-4007)5巻4号 Page16-24(2024.11)
2023年度
- Kadono T, Ishiki H, Yokomichi N, Ito T, Maeda I, Hatano Y, Miura T, Hamano J, Yamaguchi T, Ishikawa A, Suzuki Y, Arakawa S, Amano K, Satomi E, Mori M. Malignancy-related ascites in palliative care units: prognostic factor analysis. BMJ Support Palliat Care. 2023 Apr 20;13(e3):e1292-9.
- Takeda Y, Ishiki H, Oyamada S, Otani H, Maeda I, Yamaguchi T, Hamano J, Mori M, Morita T. Symptoms and Prognoses of Patients With Breast Cancer and Malignant Wounds in Palliative Care Units: The Multicenter, Prospective, Observational EASED Study. Am J Hosp Palliat Care. 2023 Dec 6時10分499091231219855.
- Sanomachi T, Ishiki H. Classifying and grading liposarcoma by CT. Lancet Oncol. 2024 Feb;25(2):e53.
- 石川 彩夏, 荒川 さやか, 石木 寛人, 天野 晃滋, 鈴木 由華, 池長 奈美, 山本 駿, 柏原 大朗, 吉田 哲彦, 里見 絵理子. 緩和的放射線治療とメサドンによるがん疼痛緩和後にオピオイド中止により離脱症状を呈した1例. 2023年18巻3号 p.159-163
- 松原奈穂 & 石木寛人. 特集●意外と知らない外用薬の知識 耳鼻咽喉科疾患に対する外用薬の効果的な使用法 がん性疼痛. JOHNS 40, 93–96 (2024).
- 阿部晃子 & 石木寛人. 薬剤性錐体外路症状/ミオクローヌス. 緩和ケア 33, 320–326 (2023).
- 石川彩夏 & 石木寛人. メサドンを使いこなして難治性疼痛を緩和しよう. 緩和ケア 33 suppl, 13–18 (2023).
- 【優秀演題】鈴木 由華, 石木 寛人, 石川 彩夏, 荒川 さやか, 天野 晃滋, 松岡 弘道, 里見 絵理子. 難治性がん疼痛に対するメサドンの有効性の検討. 第28回日本緩和医療学会学術大会. 2023 神戸
- 【優秀演題】竹田 雄馬, 里見 絵理子, 沖田 将人, 開田 脩平, 足立 大樹, 鈴木 洸, 小川 由佳, 日下部 明彦, 阿部 晃子, 木内 大佑, 石木 寛人, 天野 晃滋, 市川 靖史. 高齢者施設における緩和ケアの現状と課題に関する全国アンケート調査. 第28回日本緩和医療学会学術大会. 2023 神戸
- 戸田 雄, 石木 寛人, 天野 晃滋, 荒川 さやか, 岩田 慎太郎, 小林 英介, 小倉 浩一, 尾崎 修平, 福島 俊, 川井 章, 里見 絵理子. 四肢発生悪性骨軟部腫瘍切断後難治性疼痛に対する鎮痛薬使用の検討. 第28回日本緩和医療学会学術大会. 2023 神戸
- 山口 曜, 石木 寛人, 竹田 雄馬, 石川 彩夏, 鈴木 由華, 池長 奈美, 飯田 郁実, 前原 朝美, 荒川 さやか, 天野 晃滋, 里見 絵理子. オピオイド誘発性便秘に対する便秘薬や緩下剤の内訳と使用順序について. 第28回日本緩和医療学会学術大会. 2023 神戸
- 石川 彩夏, 石木 寛人, 鈴木 由華, 池長 奈美, 飯田 郁実, 荒川 さやか, 天野 晃滋, 里見 絵理子. オピオイド過量症状に対してナロキソンを用いた症例の検討. 第28回日本緩和医療学会学術大会. 2023 神戸
- 阿部 晃子, 里見 絵理子, 浜野 淳, 横山 太郎, 開田 脩平, 足立 大樹, 竹田 雄馬, 天野 晃滋, 石木 寛人, 川越 正平. 在宅医療におけるがん患者の終末期過活動せん妄の薬物治療の実態調査. 第28回日本緩和医療学会学術大会. 第28回日本緩和医療学会学術大会. 2023 神戸
2022年度
- Abe A, Amano K, Ishiki H. Prophylactic Scopolamine Butylbromide and Death Rattle in Patients at the End of Life. JAMA 2022;327(3):285.
- Abe A, Takeda Y, Ishiki H. Sublingual Dexmedetomidine vs Placebo and Acute Agitation Associated With Bipolar Disorder. JAMA 2022;328(2):213.
- Toda Y, Ishiki H, Machida T, Kawasaki N & Kobayashi E. Pain, Analgesic Use, and Patient Satisfaction With Spinal Versus General Anesthesia for Hip Fracture Surgery. Ann. Intern. Med. 2023;176(1):eL220366.
- Masuda K, Ishiki H, Yokomichi N, Yamaguchi T, Ito T, Takatsu H, Amano K, Hiramoto S, Yamauchi T, Kawaguchi T, Mori M, Matsuda Y & Yamaguchi T. Effect of paracentesis on the survival of patients with terminal cancer and ascites: a propensity score-weighted analysis of the East Asian Collaborative Cross-cultural Study to Elucidate the Dying Process. Support. Care Cancer. 2022;30(7):6233-6241.
- Abe A, Amano K, Morita T, Miura T, Mori N, Tatara R, Kessoku T, Matsuda Y, Tagami K, Otani H, Mori M, Taniyama T, Nakajima N, Nakanishi E, Kako J, Kiuchi D, Ishiki H, Matsuoka H, Satomi E & Miyashita M. Beliefs and Perceptions About Parenteral Nutrition and Hydration by Advanced Cancer Patients. Palliat. Med. reports. 2022;3(1):132-139.
- Kubo E, Ishiki H, Abe K, Kaku S, Yokota S, Arakawa S, Kiuchi D, Amano K & Satomi E. Clinical role and safety of tapentadol in patients with cancer: A single-center experience. J. Opioid Manag. 2022;18(3):273-280.
- Nishimura R, Ishiki H, Sato J & Satomi E. Dexamethasone for cancer-related dyspnoea. Lancet Oncol. 2022;23(12):e525.
- 【優秀演題】阿部晃子, 天野晃滋, 森田達也, 三浦智史, 森直治, 多田羅竜平, 結束貴臣, 松田能宣, 田上恵太, 大谷弘行, 森雅紀, 谷山朋彦, 中島信久, 中西絵里香, 角甲純, 木内大佑, 石木寛人, 松岡弘道, 里見絵理子, 宮下光令. 進行がん患者の点滴での栄養水分補給に関する信念と認識 多施設アンケート調査. 第27回日本緩和医療学会学術大会 2022 神戸
- 阿部晃子, 石木寛人, 竹田雄馬, 小林弥生子, 木内大佑, 天野晃滋, 里見絵理子, 松岡弘道, 堀口葉子, 佐々木久子. 化学療法誘発性末梢神経障害への鍼灸治療の有効性に関する後方視的調査. 第7回日本がんサポーティブケア学会学術集会 2022 下関
- 竹田雄馬, 石木寛人, 木内大佑, 天野晃滋, 里見絵理子, 田中幸介, 結束貴臣, 日下部明彦, 大久保直紀, 鈴木章浩, 徳久元彦, 小林規俊, 市川靖史. 当院の強オピオイド徐放製剤処方の実態. 第7回日本がんサポーティブケア学会学術集会 2022 下関
- 竹田雄馬, 石木寛人, 阿部晃子, 小林弥生子, 木内大佑, 天野晃滋, 里見絵理子, 田中幸介, 岩城慶大, 冬木晶子, 結束貴臣, 日下部明彦, 大久保直紀, 鈴木章浩, 徳久元彦, 小林規俊, 市川靖史. 当院でのオピオイド処方の推移 第27回日本緩和医療学会学術大会 2022 神戸
2021年
- Arakawa S, Amano K, Oyamada S, Maeda I, Ishiki H, Miura T, et al. Effects of parenteral nutrition and hydration on survival in advanced cancer patients with malignant bowel obstruction: secondary analysis of a multicenter prospective cohort study. Support Care Cancer. 2021;29(12):7541–9.
- Yokota S, Amano K, Oyamada S, Ishiki H, Maeda I, Miura T, et al. Effects of artificial nutrition and hydration on survival in patients with head and neck cancer and esophageal cancer admitted to palliative care units. Clin Nutr Open Sci. 2021;41:33-43.
- Yokoyama K, Ishiki H. Questions Regarding Patient-Reported Symptom Burden as a Predictor of Emergency Department Use and Unplanned Hospitalization in Head and Neck Cancer. J Clin Oncol. 2021;39(21):2415-2416.
- Kosaka M, Honma Y, Ishiki H. Unresolved questions regarding the promise of the TPEx regimen. Lancet Oncol. 2021;22(6):e227.
- Kosaka M, Mizutani T, Ishiki H. What Is the Optimal Treatment for Vulnerable Older Women With Ovarian Cancer? JAMA Oncol. 2021;7(11):1725-1726.
- 【最優秀演題賞】竹田雄馬, 結束貴臣, 大久保 直紀, 鈴木 章浩, 徳久 元彦, 小林 規俊, 市川 靖史, 石木 寛人, 天野 晃滋, 木内 大佑, 里見 絵理子.皮膚病変を有する終末期乳癌患者の症状と予後 多施設前向き観察研究(EASED study). 第26回日本緩和医療学会学術大会 2021 横浜
- 【優秀演題】久保絵美, 石木寛人, 神園翔, 川口崇, 荒川さやか, 横田小百合, 木内大佑, 天野晃滋, 里見絵理子. 在宅緩和医療におけるがん免疫療法の有害事象マネジメントの現状. 第26回日本緩和医療学会学術大会 2021 横浜
- 【優秀演題】増田健, 石木寛人, 横道直佑, 山口拓洋, 伊藤哲也, 鷹津英, 天野晃滋, 平本秀二, 山内敏宏, 川口崇, 森雅紀, 松田洋祐, 山口崇. 悪性腹水を有する終末期がん患者に対する腹水穿刺が予後に与える影響 第59回日本癌治療学会学術集会 2021 横浜
- 竹安優貴, 石木寛人, 荒川さやか, 横田小百合, 久保絵美, 木内大佑, 天野晃滋, 里見絵理子. 悪性胸膜中皮腫に対するオピオイド使用症例の検討. 第26回日本緩和医療学会学術大会 2021 横浜
- 横田小百合, 天野晃滋, 小山田隼佑, 久保絵美, 荒川さやか, 木内大佑, 石木寛人, 里見絵理子, 森田達也, 森雅紀. 進行頭頚部がんおよび食道がん患者に対する人工的栄養水分補給の効果の検討. 第26回日本緩和医療学会学術大会 2021 横浜
2020 年
- Usui Y, Ishiki H, Shimomura A, Satomi E. Suggestions Regarding the GEICAM/2003 -11_ CIBOMA/2004-01 Trial: Future Treatment Options for Early Triple-Negative Breast Cancer. J Clin Oncol. 2020 Apr 30;JCO.19.03406.
- Tanaka T, Ishiki H, Kubo E, Yokota S, Shimizu M, Kiuchi D, et al. Is Gefitinib Combined With Platinum-Doublet Chemotherapy a Counterpart to Osimertinib Monotherapy in Advanced EGFR-Mutated Non-Small- Cell Lung Cancer in the First-Line Setting? J Clin Oncol. 2020. 38(3):285-6
- Tateishi A, Ishiki H, Kubo E, Satomi E. EMERGING-CTONG 1103: For Achieving High-Quality Evidence in a Randomized Phase II Trial. J Clin Oncol. 2020; 38(3):285-6
- Kako J, Ishiki H, Kajiwara K. Terminal agitation and delirium in patients with cancer. Lancet Oncol. 2020;21(9):e409.
- Takamizawa, S., Ishiki, H., Shimoi, T., Shimizu, M. & Satomi, E. Neoadjuvant Cisplatin in BRCA Carriers With HER2‐Negative Breast Cancer. J. Clin. Oncol. 2020;38(23):2699–2700.
- 佐藤直子, 里見絵理子, 吉田哲彦, 清水正樹, 木内大佑, 石木寛人. ヒドロモルフォン使用例の後方視的検討. 癌と化学療法. 2020;47(12):1687–90.
- 久保絵美, 石木寛人, 横田小百合, 加耒佐和子, 臼井優子, 浅石健, 芹澤直紀, 清水正樹, 木内大佑, 里見絵理子. AYA世代における治験参加と終末期の意思決定.緩和・支持・心のケア合同学術大会2020 web開催
- 横田小百合, 清水正樹, 高田博美, 新井美智子, 吉本有希, 福永有伸, 中川加寿夫, 久保絵美, 芹澤直紀, 石木寛人, 木内大佑, 里見絵理子. 外国籍の終末期患者の対応で感じた困難感.緩和・支持・心のケア合同学術大会2020 web開催
- 芹澤直紀, 石木寛人, 清水正樹, 木内大佑, 横田小百合, 久保絵美, 浅石健, 加耒佐和子, 臼井優子, 里見絵理子, 三浦智史, 平本秀二. 緩和ケア病棟における心不全合併がん患者の特徴.緩和・支持・心のケア合同学術大会2020 web開催
- 久保絵美, 石木寛人, 山田海帆, 川口崇, 荒川さやか, 横田小百合, 木内大佑, 天野晃滋, 里見絵理子. AYA世代がん患者における終末期の意思決定. 第18回日本臨床腫瘍学会学術集会 2020 web開催
- 久保絵美, 石木寛人, 山田海帆, 川口崇, 荒川さやか, 横田小百合, 木内大佑, 天野晃滋, 里見絵理子. 思春期のがん患者における終末期の意思決定の現状. 第3回AYAがんの医療と支援のあり方研究会学術集会 2020 web開催
2019 年
- Kubo E, Ishiki H, Yokota S, Kiuchi D, Shimizu M and Satomi E. Quality of medical care in end- of-life lung cancer patients previously received immunotherapy. JSMO 2019 congress, July 18-20, 2019, Kyoto.
- 横田 小百合, 石木 寛人 , 木内 大佑 , 清水 正樹 , 久保 絵美 , 里見 絵理子.がん免疫治療を行った悪性黒色腫患者の死亡期直前の医療の質と医療連携 . 第 24 回日本緩和医療学会学術集会 2019 横浜
- 担がん患者における高カルシウム血症と予後予測因子の検討
- 加耒 佐和子, 石木 寛人 , 伊藤 公輝 , 樋口 雅樹 , 清水 正樹 , 木内 大佑 , 里見 絵理子第 24 回日本緩和医療学会学術集会 2019 横浜
- Nomura K, Yoshida T, Kiuchi D, Ishiki H, Takada H, Kojima R, Miyata K, Shimizu M and Satomi
- E. Home Care for End-of-Life AYA Cancer Patients. 16th World Congress of the European Association for Palliative Care. 2019 Berlin
- 清水 正樹 , 樋口 雅樹 , 石木 寛人 , 木内 大佑 , 里見 絵理子. 化学療法による薬剤性肝障害を契機にメサドンによる傾眠を来した1 例 . 癌と化学療法 ;2019,46(7)1211-1213.
- 野村 耕太郎 , 木内 大佑 , 石木 寛人 , 高田 博美 , 西島 薫 , 小嶋 リベカ, 里見 絵理子. 傍直腸再発腫瘍によるそう痒感を伴う直腸刺激症状に対して抑肝散が有効であった小児の1 例 . Palliative Care Research 2019. 14(1)9-13.
- Masuda K, Ishiki H, Oyamada S, Shimizu M, Kiuchi D, Satomi E. Questions Regarding the Randomized Phase II Trial of Defactinib as Maintenance Therapy in Malignant Pleural Mesothelioma. J Clin Oncol. 2019; 37(25):2293-4
2018 年
- 野村 耕太郎 , 吉田 哲彦 , 木内 大佑 , 石木 寛人 , 高田 博美 , 小嶋 リベカ, 宮田 佳代子, 清水 麻理子, 里見 絵理子.国立がん研究センター中央病院における AYA 世代がん患者の在宅医療連携についての後方視的検討. 第 23 回日本緩和医療学会学術集会 2018 神戸
- 吉田 哲彦 , 木内 大佑 , 竹村 兼成 , 安藤 弥生 , 野村 耕太郎 , 石木 寛人 , 高田 博美 , 里見 絵理子.急性リンパ性白血病に対する骨髄移植後に、ヒトヘルペスウィルス 6 の再活性化による脊髄炎となり、激しい掻痒感様の異常感覚を認めた1 例 第 23 回日本緩和医療学会学術集会 2018 神戸
- 清水正樹 石木寛人 吉田哲彦 木内大佑 里見絵理子 オピオイド誘発性便秘症(OIC)に対するナルデメジンの有効性・安全性に関する後方視的カルテ調査 第 3 回日本がんサポーティブケア学会学術集会 2018 福岡
- 樋口 雅樹、清水 正樹、木内 大佑、石木 寛人、阿部 健太郎、安田 俊太郎、先山 奈緒美、高田 博美、里見 絵理子. 緩和ケアチーム介入例における抗 PD-1 投与歴がある副腎不全の頻度と臨床像.第 1 回日本緩和医療学会関東甲信越支部学術大会 2018 東京
2017年
- 中村公子、野村耕太郎、木内大祐、西島薫、里見絵理子.がん性疼痛に対するオキシコドン塩酸塩の増量割合と鎮痛効果・副作用の関係について.第 22 回日本緩和医療学会学術集会 2017 横浜 傍直腸再発腫瘍による直腸刺激症状に対して抑肝散が有効であった小児の一例.
- 野村耕太郎、西島薫、木内大佑、中村公子、里見絵理子.第 22 回日本緩和医療学会学術集会 2017 横浜
- 張萌琳、木内大佑、西島薫、宮路天平、阿出川裕子、松下弘道、山口拓洋、里見絵理子.担がん患者における腹水濾過濃縮再静注法の有用性および影響の検討 第 22 回日本緩和医療学会学術集会 2017 横浜
2016 年
- 津下奈都子、木内大佑、西島薫、里見絵理子.高齢がん疼痛患者おける経口オキシコドン徐放製剤の効果と副作用に関する検討.第 21 回日本緩和医療学会学術集会 2016 京都
- 秋山紀子、西嶋薫、木内大祐、里見絵理子.腹部巨大腫瘍の膀胱圧迫による過活動膀胱症状に対して猪苓湯が有効であった一例.第 21 回日本緩和医療学会学術集会 2016 京都
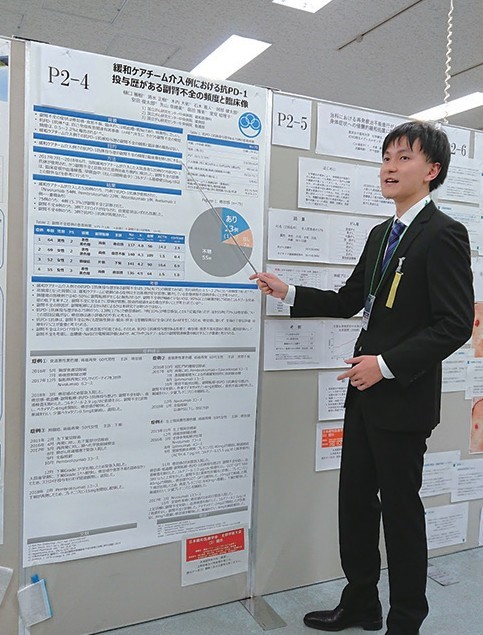
日本緩和医療学会関東地方会
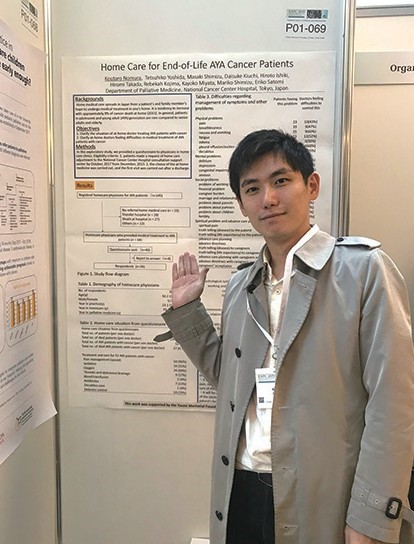
欧州緩和医療学会

英 St Christopher's Multi-Professional Academy 研修
レジデントプログラム紹介
レジデント2年コース
対象者
専門医制度対象者は基本領域専門医取得済み、もしくは取得見込み(旧専門医制度対象者はその基本領域の専門医もしくは認定医等を取得済み、もしくは取得見込み)で、当院での研修によりサブスペシャルティ専門医を目指す者
注:基本領域専門医:総合内科専門医/サブスペシャルティ専門医:緩和医療専門医、緩和医療認定医
研修目的
がん緩和ケア全般の研修を行い、緩和医療専門医または緩和医療認定医を取得するとともに、臨床研究に取り組む。
研修内容
- 1年目:緩和医療科に6か月以上在籍し診療、臨床研究等を開始する。残りの期間は緩和医療科での継続研修、CCM勤務、希望者は他科研修を行う。可能な限り、1年目在籍中に研究成果の国際学会での発表、論文執筆を行う。
- 2年目:緩和医療科・関連診療科(精神腫瘍科、放射線診断、放射線治療科等)に在籍し、緩和ケア病棟、在宅医療、非がんの緩和ケア研修については他院で交流研修を行うことも可能。
研修期間
2年間 注:そのうち一定期間の交流研修を認める 注:病院の規定に基づきCCM研修を行う
がん専門修練医コース
対象者
- 新専門医制度対象者は基本領域専門医取得済み(旧専門医制度対象者はその基本領域の専門医もしくは認定医等を取得済み、もしくは取得見込み)、かつ、サブスペシャルティ領域専門医取得済み、もしくは取得見込みで、当院での研修により当該領域に特化した修練を目指す者 注:基本領域専門医:総合内科専門医/サブスペシャルティ専門医:緩和医療専門医、緩和医療認定医
- 当センターレジデント修了者あるいは同等の経験と学識を有する者
研修目的
がん緩和ケア全般の研修を行い、緩和医療専門医または緩和医療認定医を取得するとともに、臨床研究に取り組む。
研修内容
- 1年目:緩和医療科に6か月以上在籍し診療、臨床研究等を開始する。残りの期間は緩和医療科での継続研修、CCM勤務、希望者は他科研修を行う。可能な限り、1年目在籍中に研究成果の国際学会での発表、論文執筆を行う。
- 2年目:緩和医療科・関連診療科(精神腫瘍科、放射線診断、放射線治療科等)に在籍し、緩和ケア病棟、在宅医療、非がんの緩和ケア研修については他院で交流研修を行うことも可能。
研修期間
2年間 注:そのうち一定期間の交流研修を認める 注:病院の規定に基づきCCM研修を行う
レジデント3年コース
対象者
新専門医制度対象者は基本領域専門医取得済み、もしくは取得見込み(旧専門医制度対象者はその基本領域の専門医もしくは認定医等を取得済み、もしくは取得見込み)で、当院での研修によりサブスペシャルティ専門医を目指す者
注:基本領域専門医:総合内科専門医/サブスペシャルティ専門医:緩和医療専門医、緩和医療認定医
研修目的
がん緩和ケアおよび臨床腫瘍学の研修を行い、緩和医療専門医または緩和医療認定医を取得するとともに、臨床研究に取り組む。
研修内容
- 1年目:緩和医療科に6か月以上在籍し診療、臨床研究等を開始する。残りの期間は緩和医療科での継続研修、CCM勤務、希望者は他科研修を行う。可能な限り、1年目在籍中に研究成果の国際学会での発表、論文執筆を行う。
- 2年目:緩和医療科・関連診療科(精神腫瘍科、放射線診断、放射線治療科等)に在籍し、緩和ケア病棟、在宅医療、非がんの緩和ケア研修については他院で交流研修を行うことも可能。
- 3年目:緩和医療科に在籍し、診療、臨床研究を行う。
研修期間
3年間 注:そのうち一定期間の交流研修を認める 注:病院の規定に基づきCCM研修を行う
連携大学院コース
対象者
- 新専門医制度対象者は基本領域専門医取得済み、もしくは取得見込み(旧専門医制度対象者はその基本領域の専門医もしくは認定医等を取得済み、もしくは取得見込み)で、当院での研修によりサブスペシャルティ専門医を目指す者
注:基本領域専門医:総合内科専門医/サブスペシャルティ専門医:緩和医療専門医、緩和医療認定医 - 研究・TR等に基づき連携大学院制度を利用して学位取得を目指す者
研修目的
がん緩和ケア全般の研修を行い、専門医と学位取得を目指した研究に取り組む。
研修内容
- 1年目:緩和医療科に6か月以上在籍し診療、臨床研究、TR等を開始する。残りの期間は緩和医療科での継続研修、CCM勤務、希望者は他科研修を行う。連携大学院に入学する。
- 2年目:専門医取得のための研修(希望者は緩和ケア病棟や在宅など院外研修)と、連携大学院を継続する。
- 3年目:専門医取得のための研修と、連携大学院を継続する。
- 4年目:専門医取得のための研修を修了し、学位論文を完成する。
研修期間
4年(レジデント2年+がん専門修練医2年) 注:がん専門修練医への採用には再度試験を行う 注:そのうち一定期間の交流研修を認める 注:病院の規定に基づきCCM研修を行う
レジデント短期コース
対象者
希望される期間で、がん研究センターの研修機会を活かしたい方
期間・研修方法
6か月から1年6か月。緩和医療科研修(他科ローテーションも相談可)注:6か月を超える場合は病院の規定に基づきCCM 研修を行う
問い合わせ先
緩和医療科では積極的にセミナーやイベントを主催し、情報提供を行っています。当科での研修に興味を持った方はぜひご参加ください。
教育について
セミナー・イベント
緩和医療科 科長 里見 絵理子 esatomi●ncc.go.jp