トップページ > 診療科 > 肝胆膵内科 > 中央病院 肝胆膵内科 膵がん(膵臓がん)の治療について
中央病院 肝胆膵内科 膵がん(膵臓がん)の治療について
更新日 : 2025年12月17日
目次
- 膵がん(膵臓がん)とは
- 膵がん(膵臓がん)の症状・診断について
- 膵がん(膵臓がん)の治療について
・手術による治療
・化学療法:膵がん治療の中核を担う化学療法
・内視鏡治療:症状緩和と低侵襲治療 - 膵がん(膵臓がん)の研究について
- 膵がん(膵臓がん)の療養について
- 中央病院 肝胆膵内科を受診される皆様へ
膵がん(膵臓がん)とは
膵がんは、消化液やホルモンを分泌する「膵臓」に発生する悪性腫瘍です。初期症状がほとんどなく発見が難しいため、「難治がん」の代表とされています。
国立がん研究センター中央病院の肝胆膵内科は、肝臓・胆道・膵臓領域のがんに対する化学療法(抗がん剤治療)と内視鏡診療を専門とし、日本の膵がん治療をリードする診療科です。新しい技術と豊富な経験で、この難治がんに挑んでいます。
膵がん(膵臓がん)の症状・診断について
膵がんが進行すると、腹痛、背中の痛み、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、体重減少といった症状が現れることがあります。
診断を確定させるためには、がんの組織を採取して調べる「病理診断」が不可欠です。当科では、専門性の高い内視鏡診療を駆使し、高精度な診断を行います。
- 超音波内視鏡(EUS): 口から入れた内視鏡の先端にある超音波装置で、胃や十二指腸の中から膵臓を詳細に観察します。
- 超音波内視鏡下穿刺吸引法(EUS-FNA): EUSで腫瘍を確認しながら、細い針で安全かつ確実に組織を採取する技術です。
- 内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP):胆管や膵管の中から細胞や組織を採取したり、必要に応じて胆道鏡や膵管鏡で直接観察し、診断に役立てることもあります。
これらの精密な診断が、適切な治療法を選択するための重要な第一歩となります。
詳細はEUSやERCPの内視鏡を使った診断治療のページをご覧ください。
膵がん(膵臓がん)の治療について
当院では、肝胆膵外科、放射線診断科、病理診断科など関連各科が密に連携し、「キャンサーボード」と呼ばれるカンファレンスで、患者さん一人ひとりにとってより良い治療方針を議論します。
肝胆膵内科は、このチーム医療の中核として、化学療法と内視鏡治療を担います。
手術による治療
手術は、膵がんを根治しうる唯一の治療法です。
肝胆膵内科は、手術の前後に化学療法を行うことで、外科と連携し治療成績の向上を目指します。
- 術前化学療法: 手術前にがんを小さくし、手術の成功率を高めます。
- 術後補助化学療法: 手術後の目に見えないがん細胞を叩き、再発を防ぎます。
化学療法:膵がん治療の中核を担う化学療法
肝胆膵内科の診療の柱、それが化学療法(抗がん剤治療)です。膵がんは発見された時点で手術が難しい進行・再発の状態で診断されることが少なくありません。
そのような患者さんにとって、化学療法はがんの進行を抑え、生存期間を延長し、症状を和らげるための最も重要な治療となります。
当科は、この化学療法のプロフェッショナル集団として、日本の膵がん治療を牽引しています。
1. 患者さん一人ひとりに適した治療戦略
当科では、科学的根拠に基づき、患者さんの全身状態、年齢、併存疾患、そしてがんの性質を総合的に評価し、より良い治療法を提案します。
以下に代表的な治療法(レジメン)とその薬剤を示します。
・一次治療(初回治療)
- ゲムシタビン+ナブパクリタキセル併用療法: 第一選択としてもっとも広く用いられる標準治療です。
・ゲムシタビン: 膵がん治療の基本薬の一つ。細胞分裂に必要なDNAの合成を阻害します。
・ナブパクリタキセル: 細胞が分裂する際の骨格(微小管)の働きを阻害するタキサン系の薬剤。アルブミンというタンパク質と結合させることで、がん組織に届きやすくする工夫がされています。
- FOLFIRINOX(フォルフィリノックス)療法: 全身状態が良好な患者さんに選択される、非常に強力な治療法です。4種類の抗がん剤を組み合わせ、がん細胞の増殖を多角的に抑えます。効果が高い反面、副作用も強いため、当科の専門チームによる徹底した副作用マネジメントが特に重要となります。
・オキサリプラチン: DNAの複製を阻害する白金製剤。
・イリノテカン: DNAの複製に関わる酵素(トポイソメラーゼI)を阻害する。
・フルオロウラシル (5-FU): 代謝されDNAやRNAの合成を妨げる。
・レボホリナート (l-LV): 活性型葉酸製剤で、抗がん剤ではない。フルオロウラシルの効果を高める薬剤。
・二次治療以降
一次治療の効果が乏しくなった場合でも、次の一手として二次治療(セカンドライン)があります。
治療を継続することで、より長い期間、がんと共に生きていくことを目指します。
- ナノリポソーム型イリノテカン+5-FU/LV療法: ゲムシタビンを含む治療の後に用いられることが多い標準治療です。
・ナノリポソーム型イリノテカン: イリノテカンを「リポソーム」という微小なカプセルに封入した薬剤。がん組織に長く留まり、効果の持続が期待されます。
・フルオロウラシル (5-FU) / レボホリナート (l-LV): FOLFIRINOX療法でも使用される薬剤。
・がんゲノム医療に基づく個別化治療
- BRCA遺伝子検査:膵がんの患者さんの約5%で変異が見つかります。変異が陽性の場合、プラチナ系の薬剤(膵がんでは、オキサリプラチンというプラチナ系の薬剤が保険診療で使えます)の効果が期待できます。また、プラチナ系の薬剤で効果が得られた場合、PARP阻害薬(オラパリブ)による維持療法(良い状態を長く続けるための治療)も適応になります。BRCA検査で変異が陽性の場合、ご家族(血縁者)もがんになりやすい体質である場合があるため、遺伝外来で相談することをお勧めします。
- がん遺伝子パネル検査:がんの遺伝子情報を網羅的に調べる検査です。この検査によって特定の遺伝子に変異が見つかった場合、その遺伝子変異を持つがん細胞に特異的に作用する分子標的薬の効果が期待できることがあります。これは、がん細胞が持つ特定の弱点を狙い撃ちする治療であり、まさに患者さん一人ひとりのための「個別化治療(プレシジョン・メディシン)」の実践です
2. 多職種の専門家チームによる徹底した副作用マネジメント
化学療法は効果が期待される一方で、吐き気、倦怠感、食欲不振、末梢神経障害(手足のしびれ)、骨髄抑制(白血球減少など)といった副作用を伴います。
治療を安全に、そして長く続けるためには、これらの副作用を最小限に抑える「副作用マネジメント」が極めて重要です。
当科では、医師だけでなく、化学療法に精通した専門看護師や薬剤師、管理栄養士がチームを組み、患者さんを包括的にサポートします。
新しい支持療法薬の活用はもちろん、日常生活での注意点や食事の工夫など、きめ細かなケアを提供することで、患者さんのQOL(生活の質)を維持しながら治療を継続できるよう全力を尽くします。
3. 化学放射線療法
手術はできないものの、がんが膵臓の周りにとどまっている「局所進行膵がん」に対しては、化学療法と放射線治療を組み合わせる「化学放射線療法」が有効な選択肢の一つとなります。
放射線治療科と密に連携し、適切なタイミングと方法で治療を提供します。
内視鏡治療:症状緩和と低侵襲治療
内視鏡治療は、診断だけでなく、がんによる症状を和らげるためにも重要な役割を果たします。
当科では、ERCPやInterventional EUSといった高度な手技を駆使し、患者さんのQOL(生活の質)を維持・向上させます。
1. 内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)
ERCPは、口から内視鏡を入れ、胆管と膵管の出口から細いチューブを挿入して行う検査・治療です。
- 目的: 膵がんによって胆管が圧迫され、黄疸や胆管炎が起きた場合に、ステント(チューブ)を留置して胆汁の流れを確保します(胆道ドレナージ)。
- 重要性: この処置により症状が改善し、化学療法などの本格的ながん治療を安全に開始・継続できるようになります。当科では、胃の手術後など解剖学的に難しい症例にも、高い成功率で対応しています。
2. Interventional EUS(治療的EUS)
超音波内視鏡(EUS)を診断だけでなく治療に応用する手技です。EUS-FNA(組織採取)の技術を発展させたもので、当科が特に力を入れている分野の一つです。
- EUSガイド下胆道ドレナージ (EUS-BD): ERCPによるアプローチが困難な場合に、胃や十二指腸から直接、胆管に針を刺してステントを留置します。ERCP不成功例に対する重要な代替手段であり、患者さんを救う最後の砦ともいえる治療法です。
- EUSガイド下膵管ドレナージ (EUS-PD): 膵管が狭窄し、膵炎を繰り返す場合に、胃から膵管にステントを留置します。
- EUSガイド下膿瘍ドレナージ: 膵臓の周りにできた膿のたまり(膿瘍)を、体の外から針を刺すことなく、胃や腸の中から排膿します。
これらのInterventional EUSは、体外にチューブを出す必要がないなど、従来の治療法に比べて患者さんの負担を軽減できる可能性があります。
しかし、非常に高度な技術と経験を要するため、実施できる施設は限られています。当科では、豊富な経験を持つ専門医が安全かつ確実な治療を提供しています。
膵がん治療における課題と展望
治療の課題
- 早期発見の難しさ: 有効なスクリーニング方法が確立されていません。
- 治療の副作用: 強力な化学療法には、副作用対策が不可欠です。
- 医療の均てん化: 当科が提供するような高度専門医療へのアクセスには、地域差があります。
今後の展望
- 新技術の導入: AIによる画像診断支援やリキッドバイオプシー(血液によるがん診断)など、新しい技術開発に取り組んでいます。
- 国際研究の推進: 国際共同治験をさらに推進し、新しい治療をいち早く届けます。
- 患者中心の医療: 患者さんの価値観を尊重し、共に治療方針を決定する医療を重視します。
膵がん(膵臓がん)の研究について
当科は、標準治療を提供するだけでなく、未来の治療を創り出す「研究開発拠点」としての役割を担っています。
- 新しい薬剤の開発: 国内外の製薬企業と協力し、新しい抗がん剤や免疫療法薬などの臨床試験(治験)を数多く行っています。
- がんゲノム医療: がん細胞の遺伝子異常を調べ、その結果に基づいて適切な薬剤を選択する「個別化治療(プレシジョン・メディシン)」を実践しています。
- EUSガイド下腫瘍治療: Interventional EUSの応用として、腫瘍に直接薬剤を注入したり、ラジオ波で焼灼したりする新しい治療法の開発(臨床試験)にも取り組んでいます。
集学的治療と個別化治療
手術、化学療法、放射線療法、そしてERCPやInterventional EUSといった高度な内視鏡治療を、患者さんの状態やがんの性質、遺伝子情報に合わせて適切に組み合わせる「集学的治療」と「個別化治療」を追求しています。
国立がん研究センター中央病院 肝胆膵内科の役割
- 専門性: 日本における膵がんの化学療法と、ERCPやInterventional EUSなどの高度内視鏡診療をリードしています。
- 研究と臨床の連携: 日々の診療から生まれた疑問を研究に活かし、その成果を再び患者さんに還元するサイクルを実践しています。
- 国際的な研究協力: 国際共同治験を推進し、世界の治療開発をリードしています。
膵がん(膵臓がん)の療養について
治療前後の包括的ケア
- 心理的サポート: 専門の精神腫瘍科医や臨床心理士が心のケアを行います。
- 栄養管理: 管理栄養士が専門的な栄養指導を行い、治療を乗り切る体力を支えます。
- リハビリテーション: 理学療法士が早期から介入し、体力維持・回復をサポートします。
療養についての詳細はこちら→「肝臓がん・胆道がん・膵臓がんの療養について」
中央病院 肝胆膵内科を受診される皆様へ
患者さんの選択肢を広げる取り組み
- セカンドオピニオン: 全国の患者さんからのセカンドオピニオンを積極的に受け入れ、納得のいく治療選択を支援します。
- 情報提供: ウェブサイトなどを通じ、信頼できる新しい情報を発信します。
- 患者支援プログラム: 院内の「がん相談支援センター」では、治療の悩みから臨床試験に関する情報まで、あらゆる相談に対応しています。
メッセージ
膵がんの治療法、特に化学療法や内視鏡治療、治験の情報は日々進歩しています。本ページは当科の現在の取り組みをまとめたものですが、実際の治療は患者さん一人ひとりの状態に応じて決定されます。適切な診療を受けるために、まずは当科のような専門機関にご相談ください。
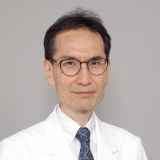
肝胆膵内科長 奥坂 拓志
専門医・認定医資格など:
医学博士
日本内科学会指導医・認定内科医
日本消化器病学会指導医・専門医
日本胆道学会指導医
日本膵臓学会指導医